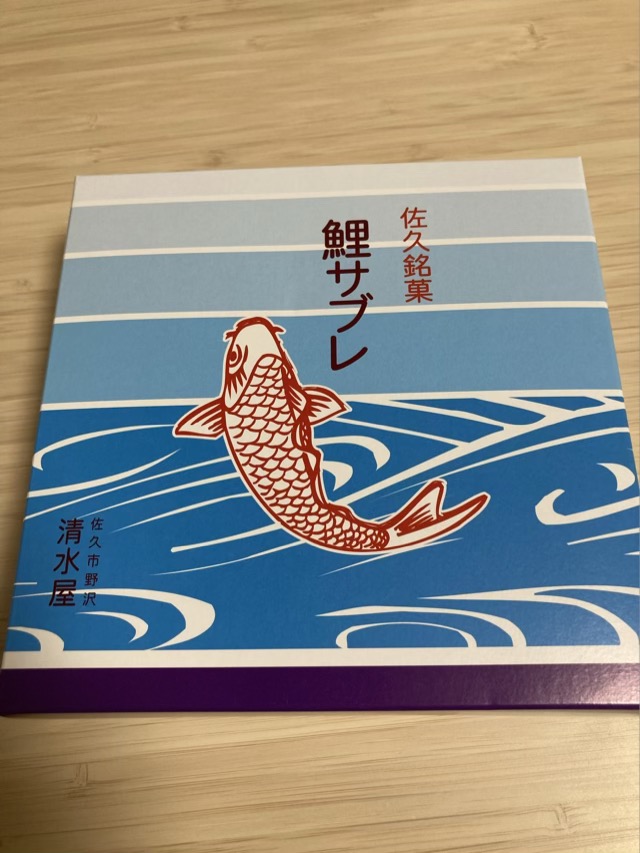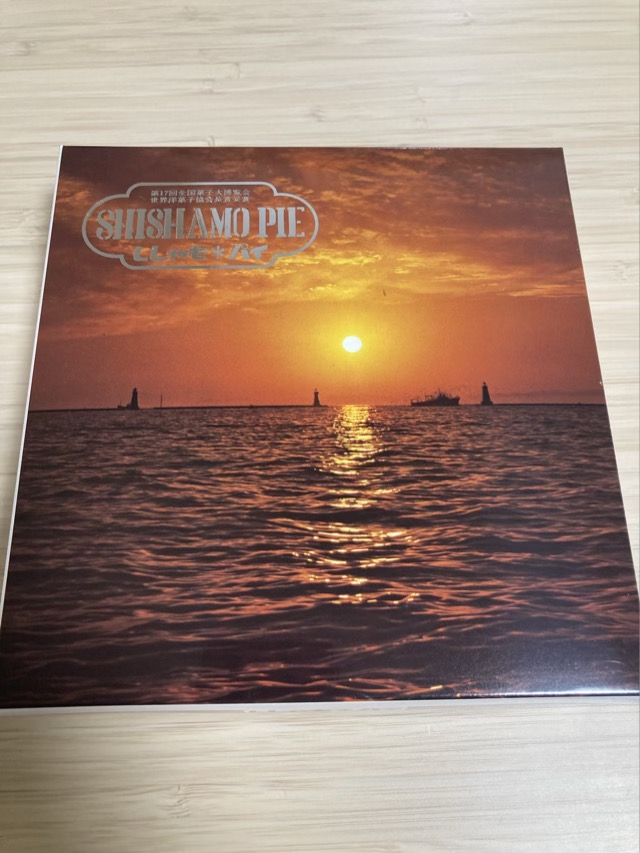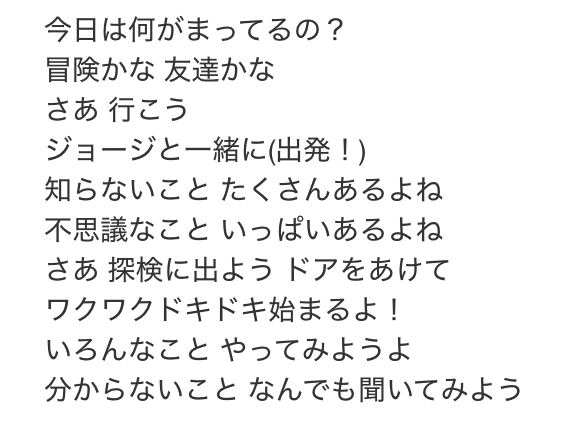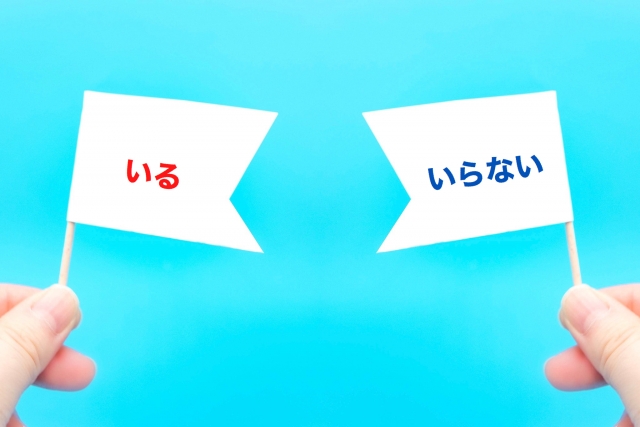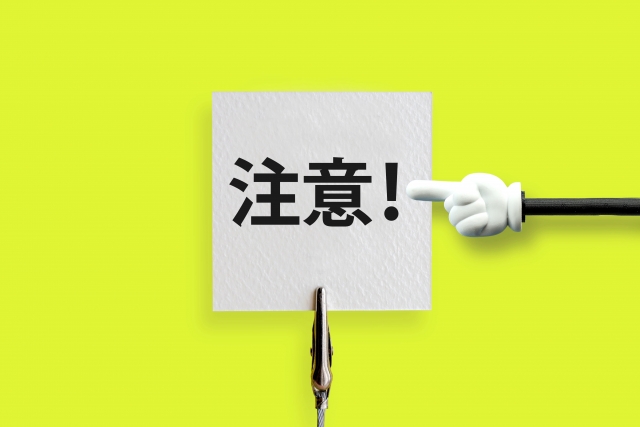大家族とは言わないかも知れませんが、子供も増えて、4人の子供とパパママの6人家族。
全く裕福ではありませんが、不思議なことに子供が1人、2人だった時よりも家計が厳しくありません。
その理由は『家と車をサイズアップしなかった』こと、この2点は本当にランクアップして買わなくて良かったです。

収入アップ、資産運用など色々頑張っていますが、特別伸びている訳でもありません。
振り返ると確実にたくさんの無駄な出費が減りました。
仕事に家庭に忙しくなるので、余計な仕事の付き合いをしなくなって、更には余計なものを買わなくなって、かなり断捨離出来たのだと思います。
やってみると無理して節約しているのでは無くて、気持ちもスッキリ快適。
その中でやっぱり効果が大きかった物が、「家」と「車」、更に物意外も言うと「保険」。

まだ子供がいなかった頃に買って夫婦2人で住んでいた小さな戸建をそのまま子供4人も増えて変わらず住んでいます。
過去の常識で考えれば、家もサイズアップしないと生活出来ないとしか考えませんでしたが、やってみると問題無く生活が出来るものです。
むしろ家計以外にもメリットが多くて、家族のコミュニケーションが多く、ケンカもするけれど比較的みんな仲が良く育っていると思います。
そして車は子供が1人2人までは軽自動車を乗っていましたが、さすがに法令遵守で3人目が生まれてコンパクトな6人乗りの車に買い替えました。
その後は子供が4人になってもコンパクトな6人乗りのまま、見た目は傷だらけでも走行上問題が全く無いのでそのままのコンパクトミニバンで生活しています。
車も家と一緒で、みんなが一緒に乗れる定員のクルマなら大きくしなくても問題ありません。
家族が増えても家と車を買い替えなくて本当に良かったと思う点は大きな出費が増えないこと。
特にランニングコストを低く抑えることが重要です。

家も車も買う時の価格ばかり気にしてしまいがちですが、大きなポイントは税金、修繕費、電気やガスなどの光熱費、広くなることによる余計な物の購入費用などの将来の出費が抑えられること。
ここが本当にポイント。
一時的な感情に流されず、家も車も新しくしたり、サイズアップをしなくて本当に良かったです。
その余計な出費が抑えられている分、たくさんの家族旅行に行ったり、新しいチャレンジにお金を使うことが出来るようになりました。
夫婦で贅沢なランチやティータイムを過ごす余裕も出来ました。
持っているだけでお金が減っていく『自分が住む家』、『自分が乗る車』は出来るだけコンパクトにしておくことが最大の節約術になりました。

意外と子供たちも大きなお家を羨ましがりますが、引っ越そうか?というと嫌と言います。
大きな家に憧れますが、慣れ親しんだ家を離れたり、大きな家で家族との距離感が離れるのは寂しいようです。
自宅、自家用車にお金をかけない分、たまに贅沢な広いホテルに泊まるくらいがちょうど良いみたいです。
車もお友達のお家の大きな車に乗せてもらって喜べるので十分かなと思っています。
更に、投資や運用を勉強しながら実践して、経済的なバランスが取れてきたら「保険」も見直すと家計改善に効果的です。

沖縄旅行ならJALで行く格安旅行のJ-TRIP(ジェイトリップ)
まだ資産の少ない状態では保険も必要ですが、ローンを組んで不動産投資を行えば生命保険の代わりに運用することも出来ますし、積み立て型の保険をやるくらいならイデコや積み立てニーサ、普通に株式投資などをやった方がよほど効率良く資産を育てられると思います。
家と車はただサイズアップしなければ簡単に節約出来ますが、「保険」に関してはそれなりにお金の勉強をやって、「保険」をかける意味、自分へのリスク、メリットを理解してから取り組む必要もあります。
小さいながらも不動産投資を始めて、イデコと積み立てニーサ、そして個別株投資も夫婦で始めて、少しずつ資産が増えてきているので損害保険以外はほとんど解約してしまいました。

ホテルが選べてフライトもJAL!格安国内旅行のJ-TRIP(ジェイトリップ)
保険で不安を守るのではなく、資産で不安を解消する発想になって、無駄な保険にお金をかけることがなくなりました。
家と車は小さくてボロボロですが、収入の割にはさりげなく贅沢な暮らしが出来ていてとても満足しています。
見栄や子供の人数が少ない時の常識にとらわれて、家と車を買い替えなくて本当に良かったと思います。
それなりに贅沢も楽しみながら、しっかりと節約するためには「車」と「家」の2点をミニマムにしおくことがかなりの効果大。
細かい部分まで節約ばかりしていると、生活が窮屈になって、ストレス発散とか、ご褒美とか理由を付けて無駄遣いを誘発するので注意が必要です。
FP3級 合格のトリセツ 速習問題集 2022-23年版 (FP合格のトリセツシリーズ) [ 東京リーガルマインド LEC FP試験対策研究会 ]